更新:2021/4/30 記事:2020/12/1
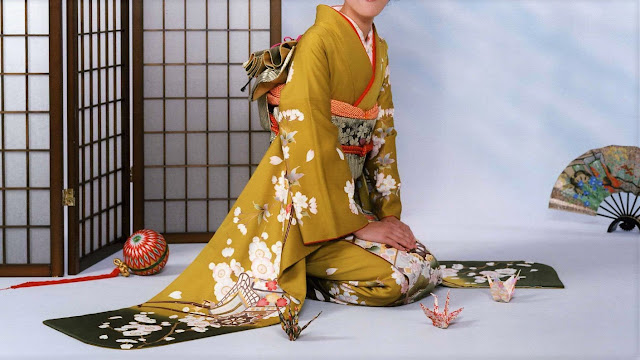 |
| 写真はイメージです。Photo by 写真AC. |
第2期:2021年~
リンク先は各作家の拠点となるサイトです。
- facebookページ:学藝理論会議 皐月会
*** 確 定 ***
- 主宰:松里鳳煌 MATSUZATO hoko(書家・文筆家・出版者)
- あ:天外黙彊 AMATO mokkyo(書家・文筆家)new
- お:大野カン ONO kan(ギタリスト・仏師)
- こ:髙堂巓古 KODO tenko(茶道家・文筆家・古書道家)
- ほ:本名カズト HONNA kazuto(音楽家・作詞家)
- ま:松里翠甫 MATSUZATO suiho(書家・ゲーマー)
- ま:MASATO MASATO(文筆家)
- み:三谷峰生 MITANI hosho(音楽家・画家・漫画家)
*** 参加予定 ***
永久会員
- 野尻泰煌(書家・藝術家)発起人・永世顧問[2019年没]
- 石丸茹園(書家・画家)[2001年没]
活動背景
- 発起人の提案していた「講師限定」案から、当初より意見具申していた限定しない「持ち回り案」へシフトする。
発表内容は「表現に限らない」自身が得意とする分野で互いの知見を広めることを目的とする。これは日本人がプレゼンが苦手なことを考慮に入れ、訓練の場としても機能させたい意図がある。
- 「発表の場を失った作家」の救済を念頭に発表の場を設けることにする。
「発表の場があるかないかで表現者は雲泥の差になる」という発起人の思想を実行する。
- 第一期の後半に重視された交流機会の創出にも力を入れる。
交流が無い限り魂のぶつかり合いには至らない為。
精神的な距離を近づけることを視野に招待制をとる。
- 現代の主流を担うジャンルにも門を広げることにする。
発起人は芸術限定を堅持し、それは誠意ある見解だったが、現代の状況を鑑みるに、芸術に至る前段階が無い限りその重要性には気づかないと考え、門戸を広げる。イラスト、漫画、映像作品、CG、Youtuber、ゲーマー(プレイで魅せる表現)も可。
第1~1.5期:2002年~2011年
- 発起人:野尻泰煌(書家)[2019年没]
- 代 表:松里鳳煌(書家)
- 東延舟(書家)
- 本名洗心(書家)[2017年没]
- 松里浩義(写真家)1.5
- 本名カズト(音楽家)1.5
- 三谷峰生(音楽家・画家・漫画家)1.5
- (その他、総合計24名)・・・雅号や芸名が無い方は非公開とします。
活動背景
講話(理論)中心の活動として開始。
これは、専門家は世間知らずな場合が多く視野が狭い問題点から来る。
後に対話形式、更に懇親会重視へシフト。
当初より会員よりゲスト参加の方が多く、セミナーは野尻泰煌を中心として開始。
セミナーの第三回以後は聞き手に松里鳳煌を配し対談形式へ。
後に始まった「藝文對談ともえ」の前身的スタイルで運用される。
後期は「交流」がメインに。

コメント
コメントを投稿